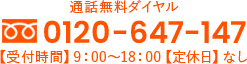よい仕事は、誰かから感謝されることで生まれます
前回、「そこらの大工や工務店じゃダメや」という風潮ができあがってしまったと言いましたよね。
こうした状況に上手く対応したのが、ハウスメーカーです。
工業化の手法をもって均一のクオリティで家がつくれるとあって、
お客様のニーズをガッチリ捉えました。
しかも、マニュアル化されているので、大工が手仕事で家を造るよりスピードも速い。
名の知れない一介の職人にお願いするより、大企業であるハウスメーカーの方が
信頼できると思われたのも無理のない状況でした。
こうした流れは高度経済成長の時代以降、長く続きました。
しかし、大工の社会にも変化が訪れたのです。
それが「プレカット」という技術。
従来は手で材木に墨付けをして、ほぞ穴を掘っていたものを機械でやれるようにしたものです。
これは、ハウスメーカーの工業化の手法を、木造の在来工法に取り入れた画期的なことでした。
現在のプレカットは、一流の大工の手法を幾度もペーストして開発されているため、
ほぞ穴にピッタリ、ビシッとはまります。
まさに一分の隙もない仕上がりが可能です。
現在ではほとんどの工務店でプレカットを採用しています。
特に若手の職人はイノベーション(改革・革新)に対するアレルギーが無いため、
よく勉強して柔軟に新しい技術を取り入れています。
今はこうした若手の大工が主力となって現場を引っ張り、
現在では職人の有様が変わってきているのです。
かつては棟上げが終わったら、棟木に幣束を立て、建物の四方にお清めの塩と酒を撒き、
大工が祝詞を詠んだものでした。
つまり、大工は神事を取り仕切っていたわけで、ある種特別な存在だったのです。
ところが、ハウスメーカーの場合、お客さんとのやり取りは営業担当者が行うことが多く、
下請けである工務店や、職人たちは、お客さんとほとんど接点がありません。
現場監督ですら、例外ではないのです。
さらに下請けの職人たちはハウスメーカーの人たちとも、まず会うことがないです。
ですから、どんな人たちが、どんな風にこの家で暮らしていくのか、
ほとんど知らずにつくっていることも少なくありません。
そうなると、丹精込めて家を造っても、誰かから感謝してもらうということがなくなってしまいます。
どんな仕事でもそうだと思いますが、仕事をする上で、お客さんに感謝していただいたり、
「誰かのためになった、よかったな」といった充足感は欠かせません。
そうした思いがあってこそ、よい仕事ができると私は信じています。
そして、人と人との関わりや、働いている人たちの気持ちのあり方から考えていかないと、
いい家を建てることはできないと思っています。
失敗しない家づくりブログその他のブログ記事